~地域から孤立した人びとへの支援について考える~
福祉関係者ら250名余が参加
| 福祉情報おきなわVol.118(2008.3.1) |
| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |
去る2月8日(金)、県総合福祉センターゆいホールにおいて、〝地域の福祉力アップ
セミナー2008〟が開催された。(主催/沖縄県社会福祉協議会)
◎セミナーの目的
本セミナーは、地域住民の自発的、主体的な参画による新たな支え合い活動を推進し、本県の福祉文化を形成していくことを目的に昨年度に引き続き開催しているものである。
地域の福祉力とは、福祉の専門職や地域住民が協働し、地域の多様な福祉課題等に対して、情報を共有し、共感し合いながら、地域の多様性や異質性を受け入れ、活動を作り出し、地域のありようを構想していく力である。
今回のセミナーでは、格差社会といわれ、生活のしづらさを訴える住民の声の高まりを貧困問題をとおして考え、専門職からの情報提供やきっかけ作りを必要とする、比較的住民による自発的な取組みが難しい課題をテーマに開催された。
| 第1部 講演 貧困問題と対峙 ~“どこからも漏れる人たち”の支援を考える~ |
湯浅氏の所属する団体では、生活に困った人からの相談を受け付けている。従来は、日雇い労働者や母子世帯など古典的な貧困層とする人びとからの相談が主だったとのことであるが、最近の傾向としては世帯構成や性別、年齢を選ばず、一つのカテゴリーでは括れない相談事例が増えており、多様化しているという。これは、日本全体が貧困化しているということだと湯浅氏は話す。
◎三層のセーフティネットから落ちていく人々の〝溜め〟のない状態
私たちは、雇用のネット、社会保険のネット、公定扶助のネットの三層のセーフティネットで守られている。しかし、今、その三層のネットがぼろぼろになって、このセーフティネットから抜け落ちて行く人が増えている。しかも、この三層に張り巡らされたネットは、3つで1セットになっているとも言われ、派遣労働者などの非正規雇用者は、失業のリスクが高く、雇用のネットから落ちやすいが、社会保険ネットの一つである失業手当が受給できない場合が多く、最後の公的扶助のネットで生活保護においても、若いから、まだ働けるから等と受け止めてもらえないことが多いのだという。若者の貧困が増えているのは、社会の構造がそうなっているからで、驚く事ではないと湯浅氏は説明する。
では、この網から漏れた人々が全て貧困状態になるかというと、そうではない。貧困に陥るかどうかの分かれ道は、彼らを支えられる家族がいるかどうかだという。家族福祉が公的なセーフティネットの肩代わりをさせられており、その負担に耐えられないケースが児童や高齢者虐待など家族間犯罪を生むのだという。湯浅氏は、貧困はお金がない状態ではなく、〝溜め〟がない状態のことだと言う。〝溜め〟とは、人を包み込んでいるバリアのようなもので、目に見えるものではないが、全ての人が〝溜め〟に包まれ、守られている。具体的には、〝金銭の溜め〟、家族や友人などの〝人間関係の溜め〟、そして自分に自信がある、気持ちのゆとりがあるといった〝精神的な溜め〟の3つ。これらの溜めが全体として失われている状態が貧困の状態なのだ。
◎生活困窮者の〝溜め〟を大きくしていくために
もやいでは、生活困窮者からの相談を受けたり、アパートの保証人になるなど、社会資源の充実を図ると共に、当事者がランチを食べに来るサロンを開き、「居場所」づくりを行い、当事者のエンパワーメントを諮っている。この社会資源の充実と当事者のエンパワーメントは、生活困窮者の〝溜め〟の拡大において、車の両輪であり、どちらか一方だけではダメだという。
例えば、生活保護を受給してアパート暮らしを始めた野宿者にとって、野宿生活にあった人との関係が途切れ、部屋で一人生活する場合、金銭的な〝溜め〟は増えても、人間関係の〝溜め〟は減ってはいないか・・・。全体的な〝溜め〟の状態を見ることが大切なのだという。
当事者のエンパワーメントは、当事者とフラットな関係で支えることの出来る民間の役割で、社会資源の充実は、公的機関の役割として充実させていかなくてはならない。
しかし、現在、相談者に合せて社会資源をつなぎ、コーディネートする役割を担う人が、どこの部署にもいないのが実情だ。縦割り行政の中で結局、たらい回しになり、どこからもこぼれ落ちてしまう人びとが出てくるのは、コーディネーター不在という問題が大きいと湯浅氏は訴えた。
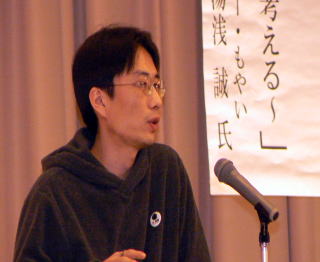
| 第2部 実践報告 孤立した人びとへの支援について |
▲講師の湯浅誠氏
(NPO法人自立生活サポートセンター・もあい事務局長)
◎ 実践報告1
「ニートと呼ばれる若者への支援活動から」 上江田 紫寿江 氏
沖縄県には、2万5千人のニートがいるといわれ、ニート率が全国一で深刻な問題となっている。卒業や中退で学校を離れた後、職業生活に入らず、職業訓練も受けないでいる若者の状況をニートとし、日本では、16から35歳が主体となっている。上江田さんは、ニート対策として厚生労働省からの委託を受けて実施している「若者自立塾」(本部町)で数多くの若者と接してきた経験から、幼少期や学齢期の様々な要因によりニートになる人が多く、心のケアを行い、やる気を起こさせるためには時間がかかるという。世間では、引きこもりを甘やかしの結果と考える場合があるが、現実は逆で親に甘えられないために発生している気がするとのこと。社会全体が彼らを理解し、彼らの社会参加への支援に取り組まなくてはならないと理解を求めた。
「ホームレス自立支援活動から」 山内 昌良 氏
県外からの移住者も増え、沖縄県のホームレスが増加傾向にあるという山内氏。以前は、ホームレスのいる公園というのは、限られた公園であったが、最近では那覇市や浦添市においては、ほとんどの公園で彼らを見ることができ、ホームレスの生活の場が分散傾向にあるという。
山内氏が代表を務めるプロミスキーパーズでは、公園を回り彼らに声をかけながら、飲食物を提供している。昨年9月には、西原町に宿泊場所を設け、51名が生活しているという。彼らへの自立支援として、資源ゴミの回収や分別作業を通じ、社会復帰へのリハビリ活動を行ったり、就職先の開拓を行っており、これまでに20名が就職や家庭復帰した。山内氏は、少しだけ誰かが力を貸すことによって、多くの人びとが社会復帰できるとし、今後は、行政とも協力しながら、ホームレスの自立支援を行っていきたいと報告した。
「支え合いマップづくりから見える地域支援」 髙野 大秋 氏
髙野氏は、地元の民生委員や地域相談センターの職員と共に、地域の中で福祉的な問題を抱えるいわゆる気になる人や地域から孤立している人と地域住民のことを良く知っている世話好きな人を印し、それぞれの繋がりを矢印で地図に書き込んだ支え合いマップづくりを行っている。
近隣住民との付き合いが苦手で地域の中で孤立している人に対しては、本人の想いを引き出しながら、その想いを実現する協力者・世話好きな方を地域住民の中から見つけ、つなげていくことが必要だという。
髙野氏はこのつなぎ役のコーディネーターが社協職員の役割であるとし、気になる人、孤立する人のニーズを解決するキーマンを民生委員や社協職員だけで担うのではなく、地域の色々な分野の世話好きさんを結びつけ、支援する側とされる側ではない、住民同士による双方向の支え合いの輪を作ることが、地域の福祉力アップにつながっていくのではないかと報告した。
▲実践報告を行う(左から)
上江田氏、山内氏、髙野氏
▲講師の話にじっくり耳を傾ける
セミナー参加者